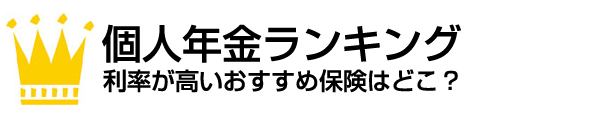確定拠出年金(個人型)とは

平成29年1月より、確定拠出年金(個人型)の加入範囲が拡大、専業主婦、公務員を含めて、60歳未満のすべての人が確定拠出年金を利用できるようになります。名称もiDeCoと決定しました。
(※厚生労働省の確定拠出年金制度を参照)
確定拠出年金は、毎月決まった額の掛金を積み立て、老後の備えをする公的制度です。
自分で老後の備えのために運用するのですが、国が認めた制度なので、色々な税制上の優遇措置が受けられます。
一番のメリットが掛金すべてが所得控除の対象となること、年間276,000円の所得控除が受けられます。
所得控除は、所得税、住民税の対象となる課税所得金額からマイナスすることができるので、掛金×所得税と住民税の税率分の減税効果があります。
所得税は、年収により最大40%の税率、住民税は一律10%の税率なので、10~50%の節税効果になります。確定拠出年金は一般的には、年間27.6万円になるので、27,600~138,000円分、税金が減ることになります。
節税分を利回りと考えると、非常に効果が高い制度です。個人年金と合わせて、老後の備えのために、ぜひ組み入れたい制度です。
確定拠出年金の拠出限度額
| 種別 | 限度額 |
| 自営業者等 | 年額81.6万円 (月額6.8万円) |
| 専業主婦、企業年金等に加入していない人 | 年額27.6万円 (月額2.3万円) |
| 企業年金に加入しており、 企業型確定拠出年金にのみ加入している人 |
年額24.0万円 (月額2.0万円) |
| 企業年金に加入しており、 企業型確定拠出年金にのみ加入している人以外 公務員・私学共済に加入している人 |
年額14.4万円 (月額1.2万円) |
確定拠出年金のメリット、節税ができる
確定拠出年金のメリットには、下記の2つがあります。
1.運用益が非課税
通常の資産運用には、利益について税金を払わなくてはいけません。銀行等の利子、株の配当金には、20%の利子税がかかりますし、株等の譲渡益についても20%の税金がかかります。 確定拠出年金は、これらが非課税になります。
2.所得税、住民税の控除が受けられる
確定拠出年金として積み立てた金額は全額が所得控除されます。
所得控除は、税金の対象となる課税所得金額から控除されるもので、確定拠出年金(個人型)の満額の場合、月23,000円、年276,000円が控除されます。これに、所得税および住民税の税率分が、実際の節税の額となります。
課税所得500万円(年収600万円程度)のサラリーマンであれば所得税の税率は20%、住民税の税率は一律10%なので、82,800円分の節税額となります。
自分の課税所得金額は、源泉徴収票で調べることができます。
給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額を引いたものです。
下記の表は、課税所得金額ごとの所得税率の表です。
自分の税率を計算して、確定拠出年金でどれだけ節税できるのか、計算してみてください。
| 課税所得金額 | 所得税率 |
|---|---|
| ~195万円 | 5% |
| 195~330万円 | 10% |
| 330~695万円 | 20% |
| 695~900万円 | 23% |
| 900~1800万円 | 33% |
| 1800万円~ | 40% |
確定拠出年金のデメリット、60歳まで引き出せない
非常に有利な確定拠出年金ですが、当然デメリットもあります。
1.基本60歳まで引き出せない
老後の備えのための公的な制度のため、基本的に60歳を過ぎないと引き出すことはできません。
また、運用期間が2年未満であれば、65歳からでないと引き出せないなど、運用期間によって、引き出せる年齢が決まってきます。
ただ、この点については、民間の個人年金保険と同様なので、この点を理解して、老後の計画を立てる必要があります。
2.運用の仕方によっては、マイナスになる可能性もある
自分で運用するので、運用結果についても自己責任となります。運用方法によってはマイナスになる可能性も当然あります。
ただ、運用可能な商品には、定期預金などの元本確保型の商品もあります。税制優遇のみを狙うなら、元本割れがしない商品を選ぶ方法もあります。
確定拠出年金の加入方法
確定拠出年金は、多くの銀行、証券会社などで加入することが可能で、平成26年10月現在202社あります。
無料で加入することができるわけではなく、手数料がかかります。
加入時にかかるのが加入手数料、国民年金基金連合会に一律2,777円必要で、金融機関によっては運営管理期間あてにさらに必要になる場合もあります。
毎月かかるのが口座管理料です。国民年金基金連合会に事務手数料が一律103円、金融機関に運営管理手数料が324円、事務委託手数料が64円の合わせて491円かかります。
ただ、金融機関によっては、口座残高にあわせて運営管理手数料が無料になるところもあります。324円ですが、毎月必要なことを考える大きな費用の差になります。
最後に給付時、支払い時です。確定拠出年金から払い戻しをした場合、給付1回につき、給付手数料がかかります。受取方法については、年金のように、毎年受け取る方法と、退職金のように一時金として全額受け取る方法があります。
確定拠出年金に関しては、総額がそれほど多くならないので、退職所得控除の税金面の優遇を考えて、一時金で受け取る方が有利かもしれません。
確定拠出年金のおすすめの金融機関
確定拠出年金のおすすめの銀行または証券会社は、手数料が安いところと、選択可能な運用方法が多いところです。
手数料については、口座残高に応じて運営管理手数料が無料になる楽天証券、SBI証券、スルガ銀行が有利です。
運用方法については、SBI証券が53本と多くのファンドから選択できるほか、楽天証券、スルガ銀行は、定期預金など元本確保商品があるメリットがあります。
主な金融機関の確定拠出年金の手数料比較
| 会社名 | 加入時 | 毎月の費用 | 受取時 |
|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 2,777円 | 167円 | 432円 |
| SBI証券 | 2,777円 | 167円 | 432円 |
| スルガ銀行 | 2,777円 | 167円 (資産50万円未満は 334円) |
432円 |
| りそな銀行 | 2,777円 | 483円 | 432円 |
| みずほ銀行 | 2,777円 | 491円 | 432円 |
| ゆうちょ銀行 | 2,777円 | 537円 | 432円 |
確定拠出年金のおすすめランキング
 SBI証券
SBI証券
 楽天証券
楽天証券
スポンサード リンク